こんにちは、文具屋のオヤジ ノボタンです。
最近、各メーカーから新しく発売されるペンを見ていると、「水性顔料インク採用」という言葉をよく目にします。
なんだか専門的な響きですが、実はこの“顔料インク”、とても面白い特性を持っているんです。
■ そもそも「顔料」って何?
インクの色のもとになるのは「色材(しきざい)」です。
この色材には大きく分けて、染料と顔料の2種類があります。
-
**染料(せんりょう)**は、水などの溶剤に溶けて、紙の繊維の中まで染み込むタイプ。
色の鮮やかさが特徴で、万年筆や水性ペンなどによく使われています。 -
**顔料(がんりょう)**は、極めて細かい色の粒子(粉)を水に分散させたもの。
紙の表面にとどまるので、光や水に強く、耐久性が高いのが特長です。
つまり、顔料インクとは“溶けない色の粒子が入ったインク”。
この粒子が、紙の上にしっかりと色を残してくれるのです。
■ 水性顔料インクとは?
「水性」と聞くと「水に弱いのでは?」と思うかもしれません。
ところが最近の水性顔料インクは、その弱点を見事に克服しています。
顔料インクを“水に分散”させる技術が進化したことで、
にじみにくく、乾きやすく、しかも発色がきれいになりました。
メーカー各社の研究によって、粒子の大きさや分散剤の改良が進み、
いまでは油性インクに負けないほどの耐水性・耐光性を実現しています。
■ 水性染料インクとの違い
| 特徴 | 水性染料インク | 水性顔料インク |
|---|---|---|
| 色の鮮やかさ | ◎ 鮮明で発色が良い | ○ 落ち着いた発色 |
| 耐水性・耐光性 | △ 弱い(にじみやすい) | ◎ 強い(長期保存向き) |
| 書き味 | なめらか、軽い | やや重め、しっかりした筆跡 |
| 向いている用途 | ノート、スケッチなど | 公文書、イラスト、宛名書きなど |
つまり、
染料インクは“鮮やかさ”、
顔料インクは“強さと保存性”。
どちらが優れているというより、用途によって使い分けるのが賢い選び方です。
■ 顔料インクの歴史と進化
顔料の歴史は古く、実は絵の具や墨も顔料の仲間です。
日本では古くから墨が使われてきましたが、あれもカーボン(炭素)という顔料が主成分。
奈良・正倉院に残る702年の戸籍用紙は和紙に墨で書かれています。
つまり顔料インクは、言ってみれば“伝統と最新技術の融合”なのです。
文具の世界では、1990年代ごろから各社が顔料インクの改良を進め、
2000年代には「耐水・耐光インク」として急速に普及しました。
■ 水性顔料インクを使った代表的なペン
-
パイロット:ジュース、ジュースアップ
発色がきれいでにじみにくく、ノートやイラストにも人気。 -
三菱鉛筆:ユニボールシリーズ
世界中で定番のゲルインクボールペン。黒の濃さと耐水性が抜群。 -
ぺんてる:エナージェル
顔料インク特有のクッキリした線と速乾性で、ビジネスシーンに強い。 -
ゼブラ:サラサシリーズ
豊富なカラーバリエーションと、安定した書き味。イラストにも人気。
これらはいずれも「水性顔料インク」の代表格。
油性ボールペンよりも書き心地が軽く、染料インクよりも色が長持ちします。
各メーカーはとても力を入れている製品で、どれも大変書き味が良く、とても人気があります。
■ まとめ ― “顔料インク時代”の到来
昔は「顔料インク=詰まりやすい」「乾きにくい」と言われた時代もありました。
しかし、いまやそのイメージは過去のもの。
メーカーの努力によって、
顔料インクは“強くて美しいインク”へと進化しました。
「にじまず、色あせない」――それが、水性顔料インクの最大の魅力です。
これからも新しいペンが登場するたびに、
その中にどんなインクが使われているのか、少しだけ気にしてみてください。
文具の世界が、またひとつ面白く見えてくると思います。
✒️ 次回予告
水性顔料インクをさらに深堀りして、
「ゲルインクボールペンの誕生」や「顔料インクの粒子技術」なども紹介予定です。

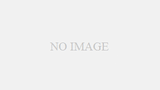
コメント