こんにちは 文具屋のおやじ、ノボタンです。
みなさんの机の中に「吸い取り紙」はありますか?
万年筆やガラスペンをお使いの方は、ブロッター(吸い取り器)にセットして使っているかもしれませんね。ですが、今では名前も使い方も知らないという方も多いかもしれません。
今日はそんな“レトロだけど実は今アツい”文具、吸い取り紙とブロッターについてご紹介します。
吸い取り紙ってどんな紙?
吸い取り紙は、万年筆で書いたインクや、ハンコを押した後の余分なインクを吸い取るための紙です。
特徴は、インクを吸っても裏に染み出さない構造。
紙の原料は木綿ぼろや化学パルプなどで、にじみ止めのサイジングを施していないため、水分をすっと吸収します。
使い方は?
吸い取り紙はそのままでも使えますが、ブロッターに取り付けるとより便利。
インクが乾ききっていない紙面の上にコロンと転がすだけで、余分なインクを吸い取り、にじみを防いでくれます。
ブロッターって何?
見た目はちょっと“黒板消し”にも似ています。
取っ手付きの木製やプラスチック製の道具で、底面に吸い取り紙をセットして使います。
木製タイプは取っ手を回して開け、曲面に合わせて紙を挟みます。
プラスチック製はパーツを外して差し込みます。
吸い取り紙・ブロッターの歴史
吸い取り紙の発祥は19世紀のイギリス。
日本では明治5年(1872年)、インクの輸入とともに普及しました。
当初は赤く染めたボロ布が使われ、現在のような白い紙ではなかったそうです。
文房具屋ノボタンの記憶
私の実家は文房具店でした。
子どもの頃の記憶の中には、ペン軸・ガラスペン・吸い取り紙・ブロッター・腕カバーなどが店先に並んでいました。
当時のガラスペンは、今のようなおしゃれなデザインではなく、竹の軸にガラスのペン先を差し込んだ実用品。
まさに佐瀬工業のような古風な品でした。
帳簿を書いたら、インクが乾く前にブロッターをコロリ…そんな光景が日常でした。
今、吸い取り紙が見直されている理由
最近、吸い取り紙が売れるようになってきました。
理由は「ガラスペン人気」と「インク沼」ブーム。
・ガラスペンや万年筆ユーザーが増加
・パイロット「カクノ」など手頃で高性能な万年筆の登場
・文具メーカーや海外ブランドがインクの新色を続々と発売中
インクを楽しむ人が増えるほど、吸い取り紙の需要も高まるのです。
おすすめのブロッター&吸い取り紙
ブロッター:
-
コレクト(木製・プラスチック製)
-
リンク
リンクエルバン(フランス、アンティーク調)
-
リンク
ボルトレッティ(イタリア)
吸い取り紙:
-
コレクト、コクヨ、クオバディスジャパンなど
-
リンクリンク
ライフ社の「スイトリシオリ」(しおりとしても使える)
まとめ
吸い取り紙は、ただのレトロ文具ではありません。
「インクをもっと楽しみたい」「紙面をきれいに仕上げたい」そんな方にとって、吸い取り紙とブロッターはなくてはならない相棒です。
昔ながらの道具が、今の文具ファンに支持されているのは、とても嬉しいこと。
みなさんもぜひ、インクと一緒に吸い取り紙を楽しんでみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
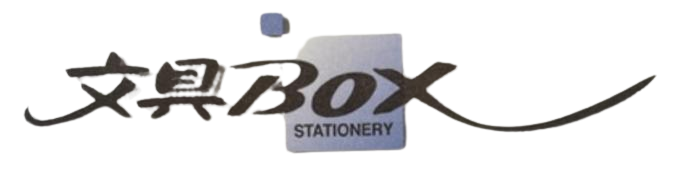

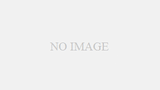
コメント