こんにちは 文具屋のおやじ、ノボタンです。
私は百貨店の文具売り場で働いていますが、今日は少し目線を変えて、化粧品売り場の“場所”にまつわるお話をしたいと思います。
先日、NHKの人気番組「チコちゃんに叱られる」を見ていたら、面白い質問が出ました。
「なぜ、百貨店の化粧品売り場は1階にあるの?」
私たちにはすっかり当たり前になっている光景ですが、言われてみれば…確かに化粧品売場ってどの百貨店でも1階にありますよね。
この“当たり前”の始まりには、ある1人の人物の工夫と、ちょっと意外な理由があったんです。
馬のフンの臭いを、香水でごまかす!?
答えはなんと、「馬のフンの臭いをごまかすため」。
時は19世紀、交通手段といえば“馬車”だった時代。
ロンドンの街中では馬が行き来し、その排泄物の臭いがあちこちに漂っていたそうです。
そして百貨店の正面玄関も例外ではなく、お客様が来る場所=馬のフンの臭いがただよう場所だったのです。
その臭いをどうにかしようと考えたのが、“百貨店の父”と呼ばれるハリー・ゴードン・セルフリッジという人物。
彼はロンドンに「セルフリッジズ」という百貨店を創業し、それまで“上流階級の女性しか入れなかった高級店”を、**誰でも気軽に立ち寄れる「楽しめるお店」**に変えようとしました。
化粧品売場を1階へ――常識をひっくり返した男
セルフリッジは、次のような数々の“革命”を起こしました。
-
化粧品売り場を1階に(→ 香りでフンの臭い対策&女性に入りやすく)
-
ショーウィンドウを装飾(→ 街ゆく人の目を引く演出)
-
飛行機を1階に展示(→ お店=体験の場という概念)
-
店内で商品を自由に見られるように(→ 今のセルフ方式の原型)
これらはすべて、「お客様が“楽しい!”と思えるようにするには?」という視点から生まれたものです。
そのなかでも象徴的なのが、「化粧品売り場を1階に移したこと」。
それまでは、化粧品はこっそり買うものであり、店の隅に置かれていたのだとか。
それを堂々と1階の正面に持ってきたのです。
香水の香りで馬のフンの臭いをごまかす、という実用面だけでなく、
女性にとって「入りやすく、選びやすい場所」を用意するという、画期的な発想でもありました。
香りと売り場、そして文具の世界へ
この話、実は文具売り場にも通じるものがあると思うんです。
文具というのは、ただ“道具”として買うものではなく、
「使って気持ちがいい」「眺めてうれしい」「贈って楽しい」という感性に響く商品なんですよね。
最近では、香り付きの文具も増えてきました。
-
香り付きの消しゴム
-
アロマ付きの便箋や封筒
-
そして、香りを楽しむための「香水インク」など
ボールペンの新製品なども、どんどん出て来ています。
そういった“感覚に訴える文具”の存在は、化粧品売り場に通じるワクワク感があります。
私の働いている文具売場でも、手に取って「わ〜素敵!」と思っていただけるよう、商品の見せ方を工夫しています。
万年筆の試し書きを用意したり、人気インクを色見本付きで展示したり。
これも、セルフリッジの「百貨店は体験の場」という考え方に通じるものがある気がしています。
「いい香り」から生まれた、今の百貨店のカタチ
化粧品売場が1階にある――それは、香りで馬のフンの臭いをごまかすという、ちょっと笑ってしまうような理由から始まりました。
けれど、その背景には**「お客様にとって心地よい場所をつくる」という真剣な想い**があったのです。
このエピソード、百貨店に勤める者としても、文具を愛する者としても、何だかとても響くものがあります。
今日のひとこと
次に百貨店に立ち寄ったとき、1階の化粧品売場の香りをぜひ楽しんでみてください。
その香りは、かつてロンドンの街を走っていた馬車と、セルフリッジという情熱の人から続いているのかもしれません――。
そしてその足で、ぜひ文具売場にもお立ち寄りくださいね。
こんな記事もどうぞ!
・『文具好き必見!お洒落で都会的なブランド「ミドリ」』
https://yamachanbungu.com/bunngusukihikken…nguburanndmidori-1526
・紫式部と文房四宝、『光る君へ」で辿る源氏物語が書かれた世界


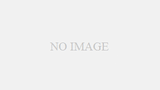
コメント